「喜名 雅 テューバ・リサイタル~謳う、テューバ~」関連企画|リサイタルをもっと楽しむ! 深“まる”アナリーゼ vol.1 喜名 雅|魅惑の低音~テューバの意外な側面を知ろう~
2024年11月2日(土)
飯山南コミュニティセンター 多目的室
お話:喜名 雅(テューバ)、新居由佳梨(ピアノ)
12月14日(土)に開催する「喜名 雅 テューバ・リサイタル~謳う、テューバ~」の関連企画として、飯山南コミュニティセンターにてワークショップを行いました。
このワークショップは、タイトルのとおり「リサイタルをもっと楽しむ!」をコンセプトに、リサイタルで演奏する曲の構成、作曲家の人物像や楽器の特徴について、演奏家自身が分かりやすくお話することで、リサイタルの予習にもなる企画です。喜名さん曰く「試食コーナー」!各作品の特徴や演奏方法などを、実演を交えながら解説しました。
ご挨拶代わりの一曲は、プログ作曲「三つの小品」より。「こんなに近くで聴けるの!?」と驚かれるほど目の前での演奏に、瞬時に引き込まれます。

テューバといえば、普段は低音部分を担当することが多い楽器ですが、「そんなイメージを変えていきたい」と語る喜名さん。
次に説明したのは、ロッシーニ作曲の歌劇「セビリアの理髪師」より“私は町の何でも屋”。バリトン歌手が歌う曲で、テューバと音域が似ているため選曲したとのこと。まさしく「謳う、テューバ」。テューバの新たな側面を感じられる一曲です。曲の最後にフィガロが早口でまくしたてるような部分では、「トリプルタンギング」という奏法が使われており、そのスピードと細かな音の粒に思わず拍手が起こります。
ここからは、テューバという楽器についてのお話です。テューバは1835年に発明された比較的新しい楽器で、香川でいうと琴平の金丸座と同い年とのこと!
テューバの音の出る仕組みを伝えるために取り出されたのは、小学校でのコンサートでもおなじみ、ゴムホースです。ホースの両端にろうととマウスピースをつけると、楽器に早変わり。音が出ている間、どれくらい振動しているかをゴムホースに触って体感していただきました。


さらに、こちらもホームセンターで購入したという塩ビパイプを繋ぎ合わせて吹いてみると、ゴムホースよりも柔らかい音が出ました。
リサイタルで演奏する本間雅智作曲「ゴムホースのポルカ」は、指を使わずに口だけで音程を変えて演奏します。果たしてリサイタルでは、ゴムホースと塩ビパイプのどちらを使って演奏されるのでしょうか。当日までのお楽しみです。
続いては、バッハ作曲「フルートソナタ 変ホ長調 BWV1031より 第一楽章」、ワーグナー作曲の歌劇「タンホイザー」より“夕月の歌”、アンジェラ・アキさんの「手紙 ~拝啓 十五の君へ~」の3曲をワンフレーズずつ演奏しました。

「ずっとさわりばっかりの演奏で、すみません(笑)。『手紙 ~拝啓 十五の君へ~』では手拍子をお願いするところがあるので、リサイタルにご来場いただいた際にはぜひ参加してください」
と喜名さん。
ここからは、スクリーンに楽譜を写して、演奏をしながら解説していきます。
テューバのために書かれたワイルダー作曲「エフィー組曲」は、小象エフィーの物語で、6つの曲で構成されています。各曲には「猿を追いかける」「恋に落ちる」「ダンスのレッスンを受ける」など、情景が浮かぶかわいらしいタイトルが付いています。
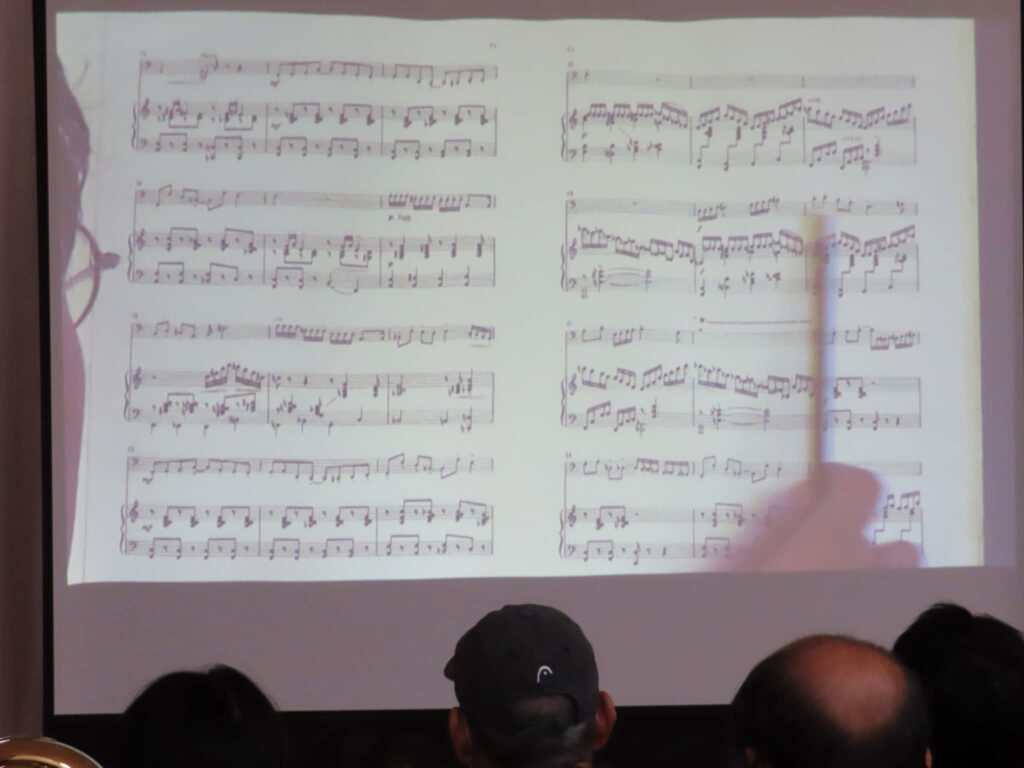
「恋に落ちる」では、憂いを感じる切ない曲調に、深いため息をあらわすような音が登場します。喜名さんは今「うどんに恋をしている」そう。
喜名さんと新居さんは、この日まで1週間丸亀に滞在し、毎日様々なうどん屋さんを巡っていたとのことで、挙げられるうどん屋さんやメニュー名に、客席のあちこちで深い頷きが見られました。
「ダンスのレッスン」では、テューバとピアノがわざとずれるように楽譜が書かれており、エフィーが上手く踊れない様子が表現されています。楽譜通りの演奏と、テューバとピアノをぴったり合わせた演奏を聴き比べてみると、まったく印象が異なります。
続いて紹介されたプログ作曲「三つの小品」は、「ヴィルトゥオーゾ的テクニックと豊かな歌心をどちらも堪能できる作品(プログラムノートより)」とあるように、第三曲では、ピアノの演奏に対して、「車の合流のようにドキドキしながら吹いている」そう。
次の作品は、テューバのソロで演奏されるペンデレツキ作曲「カプリッチョ」。この作品にはテューバの様々な奏法・音色が詰め込まれています。巻き舌のように下を震わせながら吹く「フラッター奏法」など、実際に音を出しながら解説しました。
しばらく各作品の「試食」が続いてきましたが、ここでR.V.ウィリアムズ作曲「テューバ協奏曲」より第一楽章を通して演奏しました。日本の音律にもみられる五音音階による旋律がどこか懐かしさを感じさせます。
続いての第二楽章について、「テューバの曲の中で一番好きかもしれない」と語る喜名さん。抜粋の演奏でもその美しさが存分に感じられ、客席のみなさんは大きく頷きながら聴き入っていました。
第三楽章は第一、二楽章とはまた違う目まぐるしい曲調です。その雰囲気を感じられる部分を少しだけ演奏して、テューバの演奏曲は終了です。

ここからは新居さんがピアノについてお話をしていきます。ピアノは音域が広く、同時に多くの音を出すことができます。同時に出せる音が多い分、聴かせたい音が埋もれないように、指ごとに力の強さや動かすスピードを変えて、きれいな響きを作っているそうです。

チャイコフスキー作曲「くるみ割り人形」はオーケストラ用に書かれた作品ですが、ピアノ1台でどのように表現されているのか、スクリーンに手元を映しながら解説します。「オーボエのメロディの後にハープが入ってきます」「ここは3本ほどホルンが出てきます」「ここはまた別の楽器です」と次々に表現する楽器が入れ替わりながら、10本の指で華麗に奏でられていきます。その繊細かつダイナミックな演奏に自然と拍手が起こります。
最後は、喜名さんが沖縄のご出身ということで、喜名昌吉さんの「花〜すべての人の心に花を〜」をテューバとピアノでお届けしました。朗々としたテューバと流麗なピアノの響きで会場全体が温かい雰囲気に包まれました。

質問コーナーは、テューバを演奏している中学生から練習方法について質問があり、喜名さんが丁寧に回答し、「がんばってね」と声をかける一幕も。
終演後のアンケートでは、「(テューバは)ソロ楽器としてとても魅力的だと思った」「ピアノとテューバのおもしろさが分かった」「手元や楽譜を見られてより理解できた」「本番が楽しみです」といった声が寄せられ、テューバとピアノの新たな魅力を感じられたワークショップとなりました。
